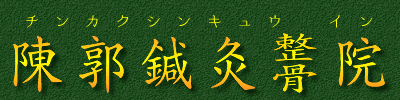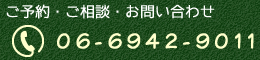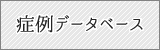ステロイドとアトピーの関係
ステロイドとは
アトピー治療に使われるステロイド剤は、化学合成されたホルモン剤です。
具体的には、副腎の外側(皮質)から分泌される「副腎皮質ステロイドホルモン」の中の「糖質コルチコイド」を人工的に作ったものです。
「糖質コルチコイド」の役割は、
- 糖質(炭水化物)やタンパク質、脂肪の代謝を調節する
- 水分やミネラル分を調節して、血圧や血液量、水分量を保つ
- ストレスに対応する
- 炎症やアレルギー反応を抑える
という4つがあります。
この最後の「炎症やアレルギー反応を抑える」という働きを狙って、アトピー治療にステロイド剤が使われています。
皮膚科領域でのステロイド外用剤の適応疾患
アトピー性皮膚炎というのは、簡単にいうと、原因がはっきりと特定できない慢性湿疹のことです。湿疹は、外の刺激に対して、生体を防衛しようとする皮膚の反応で、かゆみをともなう無菌性の病気です。このアトピー性皮膚炎の症状を軽減してくれる、対症療法としてステロイドは使用されています。
アトピー性皮膚炎以外みも、炎症やアレルギー反応を抑えるために、皮膚科ではステロイドの外用が行われています。
専門医の間では、ステロイド外用剤の効果は期待できない場合でも、病勢の経過を観察するためのステロイド外用剤の使用も行われるため、非常に複雑な使用方法となっています。
| ステロイド外用剤の適応疾患 |
|---|
| 接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、ヴィダール苔癬、貨幣状湿疹、主婦湿疹 |
| 日光皮膚炎、虫刺症 |
| 皮膚そう痒症、痒疹 |
| 薬疹・中毒疹 |
| 乾癬、類乾癬、掌蹠膿疱症 |
| 扁平苔癬、光沢苔癬、毛孔性紅色粃糠疹、シベルばら色粃糠疹 |
| 紅班症 |
| 紅皮症 |
| 円板状紅斑性狼瘡、全身性紅斑性狼瘡 |
| 天疱瘡、類天疱瘡、ジューリング疱疹状皮膚炎 |
| 円形脱毛症、尋常性白斑 |
| サルコイドーシス |
| 皮膚アミロイドーシス |
| ケロイド、肥厚性瘢痕 |
| 皮肌炎 |
◎使用されるステロイド外用剤の強さ
ステロイド外用剤の抗炎症効果には、強弱があります。
Strongestの段階に属するステロイド外用剤中デルモベートは、最強のステロイド外用剤とされており、1日10gの外用がプレドニゾロン5mg内服と同等の全身作用を発揮します。
一般には、抗炎症効果が強いほど、副作用が強く出ると考えられます。
| ステロイド外用剤の強さ | ||
|---|---|---|
| 薬効 | 一般名 | 商品名 |
| strongest | 0.05% プロピオン酸クロベタゾール | デルモベート |
| 0.05% 酢酸ジクロラゾン | ダイアコート、ジフラール | |
| very strong | 0.05% ジフルプレドナート | マイザー |
| 0.1% プロピオン酸デキサメタゾン | メサデルム | |
| 0.064% プロピオン酸ベタメタゾン | リンデロンDP、アルメタ 0.1% 10g | |
| 0.1% 吉草酸ジフルコルトロン | テクスメテン | |
| ネリゾナユニバーサル | ||
| 0.06% フルオシノニド | トプシム | |
| 0.1% アムシノニド | ビスダーム | |
| 0.1% ハルシノニド | アドコルチン | |
| strong | 0.12% 吉草酸デキサメタゾン | ボアラ、ザルックス |
| 0.12% 吉草酸ベタメタゾン | リンデロンV、ベトネベート | |
| 0.025% プロピオン酸ベクロメタゾン | プロパデルム | |
| 0.3% 吉草酸酢酸プレドニゾロン | リドメックスコーワ | |
| 0.025% フルオシノロンアセトニド | フルコート | |
| 0.1% 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | パンデル | |
| medium or mild | 0.1% トリアムシノロンアセトニド | ケナコルト、レダコート |
| 0.02% ビバル酸フルメタゾン | ロコルテン | |
| 0.1% 酢酸ヒドロコルチゾン | ロコイド | |
| 0.05% 酢酸クロペラゾン | キンダベート | |
| weak | 0.1% 酢酸デキサメタゾン | デクタン |
| 0.25% 酢酸メチルプレドニゾロン | ヴェリダムメドロール | |
| 0.5% プレドニゾロン | プレドニン | |
| 1.0% ヒドロコルチゾン | コートリル | |
◎薬理療法 長期大量療法の適応症
ステロイド療法以外に特異的な治療法がなく、ステロイド療法が主体となる病気もあります。
膠原病、自己免疫疾患、悪性の血液疾患などの病気です。
| 長期大量療法の適応症 |
|---|
| 慢性関節炎リウマチ (※) |
| エリテマトーデス(SLE) (※) |
| 結節性動脈周囲炎 |
| 皮膚筋炎、多発性筋炎 (※) |
| リウマチ性心炎 |
| 重症筋無力症 (※) |
| 自己免疫性溶血性貧血 |
| 突発性血小板減少性紫斑病 |
| 再生不良性貧血 |
| 急性白血病 |
| 慢性リンパ性白血病 |
| 悪性リンパ腫 |
| 骨髄腫 |
| ネフローゼ症候群 |
| 潰瘍性大腸炎 |
| Crohn病 |
| サルコイドーシス(重症) |
| 突発性間質性肺炎(急性型) |
| ルポイド肝炎 |
| * いわゆる膠原病とは (※) の4症に強皮症を加えたものをいう。 |
こうした病気については、ステロイド療法の中で最も重要でしかも困難な治療法となります。投与方法、離脱方法に関して工夫を必要とし、副作用に関しても予防手段を講じる必要があります。
内科的適応
| 内科的適応 | |
|---|---|
| 1 | 副腎皮質機能不全 |
| 2 | 亜急性副腎不全 |
| 3 | 各種膠原病 |
| 4 | 気管支喘息(重積発作も含む) |
| 5 | 血清病・薬物アレルギー |
| 6 | 肝性昏睡 |
| 7 | 細胆管性肝炎・肝硬変症 |
| 8 | 重症急性肝炎 |
| 9 | ネフローゼおよびネフローゼ症候群 |
| 10 | 亜急性腎炎 |
| 11 | 限局性回腸炎 |
| 12 | 潰瘍性大腸炎 |
| 13 | スプルー |
| 14 | 急性膵炎 |
| 15 | 紫斑病 |
| 16 | 後天性溶血性貧血 |
| 17 | 再生不良性貧血 |
| 18 | 急性白血病 |
| 19 | リンパ性白血病 |
| 20 | 顆粒球減少症 |
| 21 | サルコイドーシス・好酸性肉芽腫 |
| 22 | リンパ肉腫・細網肉腫・ホジキン病 |
| 23 | 多発性硬化症・視束脊髄炎・急性球後視束炎 |
| 34 | 脳脊髄炎・ギランバレー症候群 |
| 25 | 末梢性顔面神経麻痺 |
| 26 | 筋強直症 |
| 27 | 精髄くも膜炎 |
| 28 | うっ血性心不全 |
| 29 | 亜急性甲状腺炎 |
| 30 | 肺線維症 |
| 31 | 肺結核(しん出型・粟粒型) |
| 32 | 結核性髄膜炎 |
| 33 | 結核性胸膜炎 |
| 34 | 結核性心包炎 |
| 35 | 結核性腹膜炎 |
| 36 | 重症感染症(急性伝染病を含む) |
| 37 | 放射線性宿酔 |
| 38 | 副腎皮質ホルモン中止時前後 |
| 39 | 原因不明の発熱 |
| 40 | 癌末期・脊髄腫瘍 |
何故ステロイドが危険なのか
ホルモンは、ごくわずかな量で作用します。
体内での量が多すぎても、少なすぎても体の働きに支障をきたします。
合成されたホルモン剤であるステロイド剤も量を間違うと、身体に支障が出てきます。
ステロイド剤を投与することが、間脳、下垂体、副腎機能の抑制を引き起こすためです。
こういったホルモンサイクルが壊されることによって、さまざまな症状があらわれてきます。
◎副作用:クッシング症候群
ステロイド剤を長く使っていると、糖質コルチコイドの過剰分泌でおこる「クッシング症候群」と似たような副作用がおこります。症状としては、次のようなことが起こってきます。
中心性肥満・・・手足がやせた体幹部だけの肥満体型
ムーンフェイス・・・顔に脂肪が沈着してまん丸く腫れ上がります。
糖尿病
高血圧
免疫力の低下
不眠、うつ
骨粗鬆症
皮膚の病状・・・色素沈着、多毛症
消化性潰瘍・・・胃や十二指腸の潰瘍
白内障、緑内障
無菌性骨頭壊死
精神異常
| 副腎皮質ステロイド療法の副作用とその発症機序 | ||
|---|---|---|
| 系統 | 副作用の内容 | 推定される発症機序 |
| 目 | 緑内障 | 眼圧の上昇 |
| 白内障 | 水晶体線維の凝固・壊死(?) | |
| 皮膚 | 創傷・術創の治癒遅延、皮下出血、皮下組織委縮、皮膚菲薄化、皮膚線条 | 線維芽細胞の増殖抑制、膠原線維の合成阻害、肉芽の退縮 |
| ざ瘡、多毛 | 軽度のアンドロゲン様作用 | |
| 筋 | ミオパチー、筋委縮 | 白筋における糖新生の障害、蚤白異化、低K |
| 骨格 | 骨粗鬆症、脊椎圧迫骨折 | 蚤白異化、骨Caの吸収促進、負のCa平衡 |
| 無菌性(虚血性)骨壊死:特に大腿骨頭壊死 | 骨端部血管内の脂肪塞栓、血行途絶 | |
| 消化器系 | 消化性潰瘍:特に胃潰瘍、消化管粘膜出血、腸穿孔 | 塩酸分泌促進、粘液分泌低下、結構障害、抗肉芽、プロスタグラジン合成抑制 |
| 脂肪肝、急性膵炎 | 脂肪沈着、脂肪塞栓、血行障害 | |
| 中枢神経系 | 精神障害(うつ状態→自殺企図、躁状態、分裂病様)、多幸感、異常食欲亢進(→肥満)、不眠 | 神経伝達物質への影響、シナプスの神経伝達潜伏時間の延長 |
| 脳圧亢進、偽脳腫瘍症状、けいれん、てんかん様症状 | 脳圧の亢進、脳内の水・電解質代謝異常 | |
| 循環系 | 高血圧、Na・水貯溜(→浮腫)、低カリウム血症 | 軽度の鉱質ステロイド様作用 |
| 代謝系 | ステロイド糖尿、潜在性糖尿病の顕性化、真性糖尿病の増悪、ケトアシドーシスの誘発、非ケトーシス・高浸透圧性昏睡の誘発 | 肝における糖新生の促進、抗インスリン作用、食欲増進効果 |
| 高脂血症(コレステロール、TG増加)、中心性肥満、満月様顔貌 | 四肢皮下脂肪の脂肪分解→く幹・内臓への動員 | |
| 内分泌系 | 成長抑制(小児)、月経異常・続発性無月経、間脳・下垂体・副腎系の抑制(→医原生副腎不全、副腎クリーゼ、ステロイド離脱症候群の発症) | 間脳・下垂体抑制作用(ACTH、GH、TSH、ゴナドトロピンなどの分泌抑制)、副腎への直接の抑制作用 |
| 血管系 | 血栓形成、血栓性静脈炎、塞栓、梗塞 | 凝固因子の増加、抗プラスミン作用、血管壁の変化 |
| 血液像 | 白血球(とくに好中球)増加、好酸球・リンパ球の減少 | 好中球の生成・骨髄からの動員の促進、リンパ球生成抑制 |
| 免疫系 | 免疫反応の抑制、遅延型アレルギー反応の減退、各種感染症(化膿菌、結核菌、真菌、ウイルス、原虫など)の誘発・増悪 | リンパ球・単球の減少、抗体産生の抑制、抗原抗体反応の抑制、白血球・マクロファージの遊走抑制、その他 |
◎小児科領域の副作用
| 比較的よく見られるステロイド剤の副作用 | ||
|---|---|---|
| 1 | 全身面、代謝系 | |
| クッシング様容貌 | ||
| 肥満 | ||
| 成長障害 | ||
| 高血糖 | ||
| 2 | 中枢神経系 | |
| 気分変調 | ||
| 不機嫌 | ||
| 抑うつ | ||
| 3 | 皮膚 | |
| 菲薄化 | ||
| 線条 | ||
| 紫斑 | ||
| 4 | 内分泌系 | |
| 間脳・下垂体・副腎機能の抑制 | ||
| 性発達の遅延 | ||
| 5 | 目 | |
| 白内障 | ||
| 6 | 消化器 | |
| 消化性潰瘍 | ||
| 7 | 筋 | |
| ミオパチー | ||
| 8 | 骨 | |
| 骨粗鬆 | ||
◎副腎機能の低下
副腎が長期間、ホルモンを分泌しないようになると、その機能が衰え、やがて副腎自体が委縮してしまいます。
<考察> 薬理学的特徴及び副作用
ステロイド剤を投与すると、下垂体・副腎系を中心として、生体の内分泌系に多くの影響を与えます。ACTHの分泌が抑制されるだけでなく、成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモンの分泌も抑制されるのです。一方、グルココルチコイドの作用に拮抗するインスリン分泌を亢進させ、糖尿病へと移行していきます。

また、ステロイド剤は多くの疾患に用いられていますが、いずれも根治的に作用するのではなく、あくまで抑制的に作用するという特徴があります。
疾患に伴う病状、病変を軽減、改善はしますが、疾患の原因を除去することはできないのです。
そのため、病勢が活動性である場合は、投薬を中止すると必ず再発がおこります。
ホルモンとしての抗炎症作用以外の作用をもたない、抗炎症作用のみが顕著なステロイド剤の開発が成功すれば良いのでしょうが、その可能性はホルモン剤としての限界を考えると非常に可能性は低いといわざるをえません。